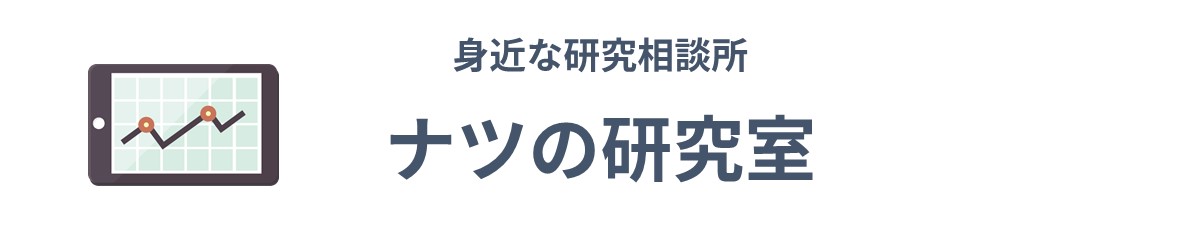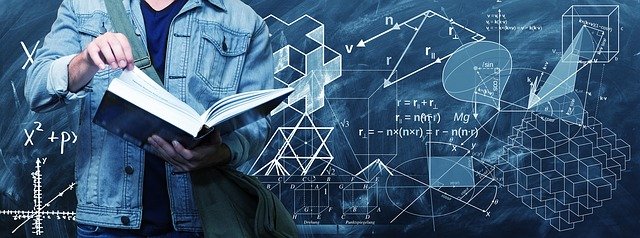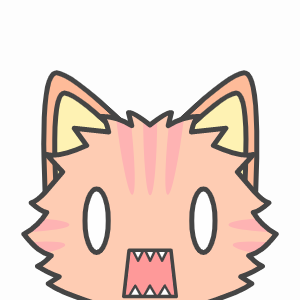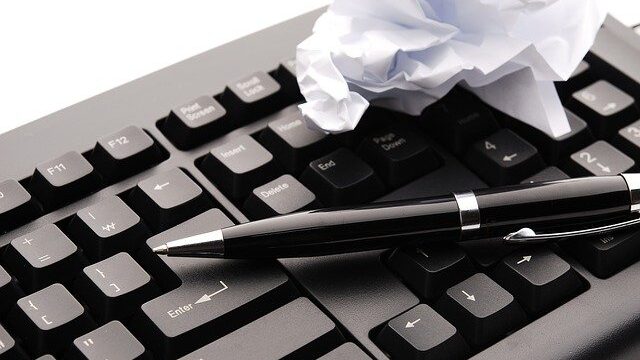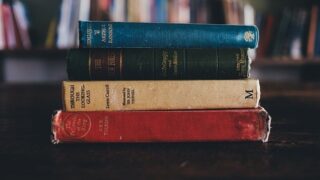今日はどうしたのー?
初めての研究では何から手を付けて良いのか分からず途方に暮れている人が多いと思います。
実際、研究をする必要がある人って意外と少ないと思いますが、する必要がある人にとってはものすごく高いハードルになってしまいますよね。
この記事では、初めて研究をする人、研究の進め方に困っている人に向けて、まずはデータがとれるようになるまでの研究の進め方を4つのステップで解説していきます。
ステップ1:研究テーマを決める
 研究テーマ、すなわち何を研究するかを決めることはとても重要です。
研究テーマ、すなわち何を研究するかを決めることはとても重要です。
現状の問題は何かを考えて、問題を解決するために何を明らかにするのかについてしっかりと考えていきましょう。
日頃、何か疑問に思ったり、知識や経験ではどうしても解決できないことはないでしょうか。
そういったものはすべてが研究テーマになりえます。
日頃から意識して、活動をしてみてください。
また、卒業研究を行う大学生や初めて研究をする医療関係の職に就いている人なんかは指導教授やバイザーがテーマを用意してくれることもあるかもしれません。
それに乗っかってしまうのも全然アリだと思います。
まず、研究に触れてみるっていうもの貴重な経験ですからね。
ただ、それはあくまで研究の骨格に過ぎません。
与えられたテーマでも具現化していくのは自分ですよ。
FINER基準
F:Feasible = 実行可能である
I:Interesting = おもしろい/興味深い
N:Novel = 新しく独創的である
E:Ethical = 倫理的である
R:Relevant = 切実である
ステップ2:関連研究について調べる

研究テーマが決まったら次は関連研究について調べていきましょう。
ステップ3:研究デザインを決める
 研究テーマが決まって、関連研究もしっかり調べることが出来たなら、次は研究デザインを決めていきます。
研究テーマが決まって、関連研究もしっかり調べることが出来たなら、次は研究デザインを決めていきます。研究デザインの型
研究デザインの型として
-
症例報告
-
シングルケーススタディ
-
観察研究
-
調査研究
-
介入研究・実験研究
-
メタアナリシス
-
システマティックレビュー
-
質的研究
などがあります。
細かい内容についてはこの記事では触れませんが、どの研究手法が最も自分の疑問を解決してくれるか検討してみましょう。

ステップ4:研究計画書に起こす

研究テーマの選定、関連研究調査、研究デザインの選定が終われば、いよいよ最後のステップです。
まとめ
【ステップ1:研究テーマを決める】
FINER基準を参考に、リサーチクエスチョンを洗練する
【ステップ2:関連研究について調べる】
何が分かっていて、何が分かっていないのか、自分の研究がどのように寄与していくのかを吟味する
【ステップ3:研究デザインを決める】
型に沿って研究手法を決めていく
【ステップ4:研究計画書に起こす】
研究計画書は研究の道しるべ